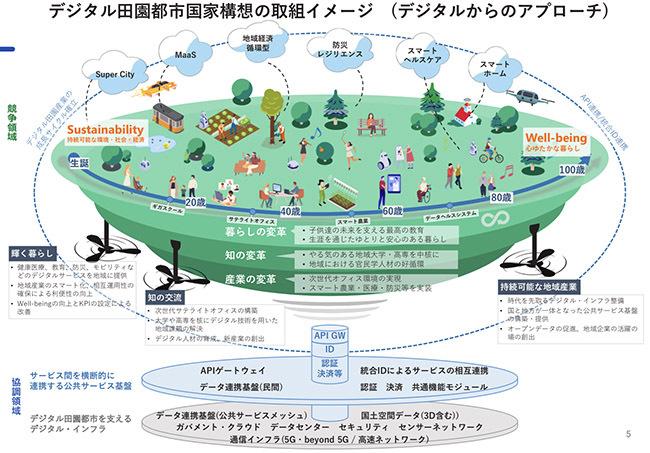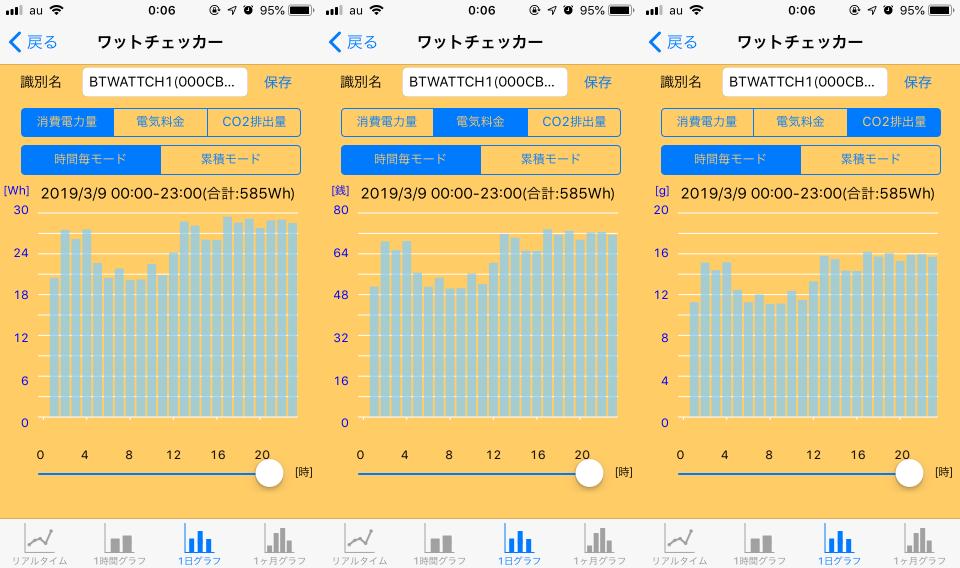ポルノではなく芸術、世界の官能映画30選
「芸術vsポルノ」という概念に挑み、物議を醸した映画は数多い。フルヌード、官能的な3P、金儲け目当てのセックスシーンなど、ポルノ映画と呼ばれてしまうシーンはあれど、芸術作品として今もシネコンで上映され続けている作品もあるのだ。今回は、ローリングストーン誌が厳選した官能映画30本を紹介する。
※本記事は、2014年3月18日に米ローリングストーン誌に初出。
高い期待、過剰な宣伝、頭から紙袋を被った姿で公式の場に現れる主演俳優など--上映時間5時間におよぶラース・フォン・トリアー監督の壮大な2部作『ニンフォマニアック』(2013年製作/2014年公開)の第1巻が劇場で公開された。物議を醸すことを避けるというより、全力でそれを狙っているかのようなデンマークのフォン・トリアー監督が放つ『ニンフォマニアック』はひとりの女性の性の目覚めを描いた壮大な物語で、作品のいたるところにスパンキング、フェラチオ、メナージュ・ア・トロワ、アナルセックス、マスターベーション、そして古き良きスタイルのセックスが散りばめられている。なかにはセックス専用のスタントを起用した場面もあるが、観客の目の前では、シャルロット・ゲンズブールとシャイア・ラブーフといった俳優たちによる、ポルノ俳優顔負けの非擬似セックスが繰り広げられる(同作のオーディションの際、ラブーフは自家製のポルノ動画まで送った)。
ありあまるほどの露骨な性描写にもかかわらず、フォン・トリアー監督の『ニンフォマニアック』はポルノ映画ではない。むしろ『ニンフォマニアック』は、”メジャー”と呼ばれる映画が表現できる限界に挑んだ無数の作品のひとつであり、ネット上でクレジットカード情報を入力してから観る類の映画と同じように扱うべきものではない。『ニンフォマニアック』のような作品のキャストは超一流で、どれもワールドクラスの名監督が手がけている。シネコンと単館映画館の両方で上映されるべき作品なのだ。そのなかには一流の外国映画として輸入されたものもあれば、ハリウッドのスタジオでプロデュース・制作されたものもある。だが、今回紹介する30本にはひとつの共通点がある。それは、メジャーな官能映画の限界ギリギリに挑戦したことだ。愛する人と一緒に今回の閲覧リストをお楽しみいただきたい。
>>すべての画像を見る
1.『私は好奇心の強い女−イエロー篇』(1967)Photo: Mary Evans/Ronald Grant/Everett Collection
政治とセックスを描いたスウェーデンのビルゴット・シェーマン監督のメロドラマ映画『私は好奇心の強い女−イエロー篇』が1969年にアメリカの検閲に引っかかった原因は、陰毛の描写だけではなかった。同作は、最高裁判所が取り扱うわいせつ事件にまで発展し、いまでも映画史上最大の問題作のひとつとされている(レナ・ナイマンとボリエ・アールステットが陰毛の一部を見せたことは、スウェーデン映画がほかの外国映画と一線を画すことを証明する上で間違いなく一役買った)。妻帯者の男と関係を持つ好奇心旺盛な女子学生を描いた同作が検閲で問題になったのは、ナイマンが共演者の丸見えの男性器にキスをするシーンがあったからだ。そのシーンに対する批判が殺到したものの、最終的には検閲という障壁が取り払われ、映画において寛容な表現が許される時代が訪れた。同作を観た人は、誰ひとりとしてキング牧師のインタビュー映像、ベトナム反戦運動の映像、気の利いた反権威主義的なユーモアについては語らず、ただ性器のシーンだけに注目した。だが、好奇心と論争のおかげでより多くの人が観る結果となった。後は知ってのとおりだ。(Writer: DAVID FEAR)
2.『アメリカを斬る』(1969)Photo: Courtesy of Everett Collection
シネマトグラファーから映画監督に転身したハスケル・ウェクスラー監督による、フィクションとノンフィクションが織りなす『アメリカを斬る』(1968年のシカゴ民主党大会で実際に起きた暴動の映像も含む)は、リアルなシチュエーションで触れ合う俳優たちの演技を観る緊張感に支えられている。だが、あるシーンがいくらか生々しすぎるとアメリカ映画協会(MPAA)委員会に目をつけられた。そのシーンとは、のちにタランティーノ監督の寵児となるロバート・フォスターとマリアンナ・ヒルが丸裸でセックスに興じ、文字通りシーツに絡まりながら事を終える場面だ。まるでドキュメンタリーのようにリアルなふたりの逢引のシーンのせいで同作はX指定(成人向け)となったが、ウェクスラー監督はそれよりも劇中の政治的な怒りの表現がX指定の原因だと主張した。それでも、やはり例のセックスシーンに何らかの原因があったというのが本誌の見解だ。(Writer: DAVID FEAR)
3.『恋する女たち』(1969)Photo: Copyright © Courtesy Everett Collection/Everett Collection
イギリスの作家・詩人・批評家のD・H・ローレンスの同名小説を見事に映画化したケン・ラッセル監督の『恋する女たち』は、エキセントリックなラッセル監督が手がけた、控えめで”上品な”作品のひとつとされてきた。アラン・ベイツとオリバー・リードの裸のレスリングのシーンを除いてはーー。多くの人にとってこのシーンは、メジャー映画で男性のフルヌードが初めて披露された場面でもある。このシーンには、次のような逸話がある。ベイツとリードは撮影に乗り気ではなかったが、ある夜ふたりは酔っ払って一緒に用を足しに行き、それぞれの下半身をチェックした結果、何も気にすることはないという結論に至った(リードが「もっと意味深に見えるように何とかして半立ちにし、ガールフレンド全員から『やめときなよ』と見捨てられないよう必死だった」と言ったように、彼はテイクの合間に現場を離れていたことを踏まえると、実際には気にしていたのかもしれない)。このシーンはプラトニックな男の絆を描いているが、いま観ても同性愛の要素があることは一目瞭然だ。事実上の男と男のセックスシーンである。(Writer: BILGE EBIRI)
4.『ラストタンゴ・イン・パリ』(1972)Photo: Courtesy of United Artists
ストラヴィンスキーの「春の祭典」のようにセンセーショナルではなかったにせよ(米映画評論家のポーリーン・ケールが当時このように評価したのは有名な話)、ベルナルド・ベルトルッチ監督の独創的な『ラストタンゴ・イン・パリ』は、映画の性描写の潮流を変えた作品だった。イタリア出身のベルトルッチ監督は当初、ドミニク・サンダとジャン=ルイ・トランティニャンというふたりのフランス人俳優を主役に起用したいと考えていた。だがサンダは妊娠したばかりで、トランティニャンはヌードNGだった。そこで監督は新進気鋭のマリア・シュナイダーを、さらにはマーロン・ブランドを起用して人々を驚かせた。まもなくしてブランドは、『ラストタンゴ・イン・パリ』を通じてより魅力的で深みのある瞑想的なイメージを確立した。同作でブランドは妻に先立たれ、人生に疲れ果てた中年男を演じている。この名もなき男は、パリのアパルトマンの空室で出会った若い女性とのアスレチックで概してクリエイティブな逢瀬に世界からの逃避を求める。当時の観客は、大物映画スターが肛門に指を入れられるシーンに慣れていなかった。いま観ると同作のセックスシーンはどちらかといえば控えめだが、いかにして肉欲が境界を破壊するかを追求した点では、いまでも一見の価値がある。一度観れば、「バターを取ってきてくれ」ということばの捉え方が永遠に変わってしまうだろう。BILGE EBIRI
5.『赤い影』(1973)Photo : Copyright © Everett Collection/Everett Collection
超常現象を描いた、ニコラス・ローグ監督の血も凍るほど恐ろしいスリラー映画『赤い影』には、映画史上屈指と呼べるセックスシーンが潜んでいる。同作でドナルド・サザーランドとジュリー・クリスティは、娘の事故死の後にベネチアに移住する夫婦を演じている。死んだ娘の亡霊が見えると言うイギリス人の霊媒師の女のせいで日常がほころび始める前、サザーランドとクリスティは服を脱いで夫婦の営みに興じる。見事なディテール(クリスティの首もとを濡らす唾液や体位を変えるごとにふたりが交わす微笑みなど)はもとより、このシーンを素晴らしいものにしているのは、セックスの合間とその後のローグ監督のインターカットによる切り替えだ。この映画のどこがポルノまがいなのか? とあなたは疑問に思うかもしれない。のちにサザーランドは、このシーンの撮影の際に実際にカメラの前でクリスティと愛を交わしたと主張した。この発言はその後何年にもわたって否定されては、立証されてきた。こうしたことを踏まえると、まるで他人のセックスを覗き見しているような奇妙な興奮をいまも感じる。(Writer: ERIC HYNES)
6.『ソドムの市』(1975)Photo : Copyright © Everett Collection/Everett Collection
1970年代初頭、イタリアの映画監督で詩人・作家・評論家のピエロ・パオロ・パゾリーニは、”生の3部作”と称された作品--古典的艶笑文学作品をあふれんばかりの露骨なセックス描写とともに映画化した『デカメロン』(1972)、『カンタベリー物語』(1973)、『アラビアンナイト』(1974)--でセンセーショナルな興行成績を残した。だが、陽気ではつらつとした3部作に続いてパゾリーニ監督が世に放ったのは、映画史上もっともショッキングで退廃的な作品のひとつと言える『ソドムの市』だった。短命に終わったムッソリーニ政権下の北イタリアを舞台に、同作では若い少年少女を監禁し、性的暴行を加えて陵辱・拷問した挙句におぞましい方法で殺害する4人の権力者が描かれる。同作はまともに見ることさえままならない作品だが、これはパゾリーニ監督の意図でもある。というのも、パゾリーニ監督は資本主義が人間に対して行っていると感じたことを恐ろしい寓意を込めて観客の目の前にさらけ出したのだ。徹底した恐怖のサディズムとマゾヒスムを観れば、監督の意図が十分に伝わってくる。(Writer: BILGE EBIRI)
7.『愛のコリーダ』(1976)Photo : Courtesy Everett Collection
ご存知のとおり、ポルノ映画は汚れたレインコートに身を包んだ男たちでいっぱいのいかがわしい映画館で上映されるものだった(少なくともAV時代以前は)。ニューヨーク映画祭(NYFF)でポルノ映画が上映されることはなかった。この由緒正しい映画祭が、当時のメディアを大いに賑わせた、芸妓と雇い主のあいだで起きた”阿部定事件”を題材とした大島渚監督の『愛のコリーダ』を上映するということは、同作はポルノ映画ではないのだ。NYFFの承認と、日本が生んだもっとも偉大な映画監督のひとりである大島渚がこの極めて過激なドキュメンタリー・ドラマを手がけたという事実にもかかわらず、俳優たちがノンストップで性行為に及ぶ姿を映した同作は、税関職員から「わいせつすぎる」とみなされ、のちにNYFFは上映を中止した。その後は「芸術か、わいせつか」をめぐって裁判闘争にまで発展し、最終的に大島監督は無罪判決を受けた。いまでは実在の犯罪事件を描いた名作として正当に評価されている。芸術対ポルノという概念に挑んだ映画があるとしたら、『愛のコリーダ』はまさにその代表例である。(Writer: DAVID FEAR)
8.『カリギュラ』(1979)Photo : Mary Evans/FELIX CINEMATOGRAFICA/PENTHOUSE FILMS
米アダルト雑誌・ペントハウスのオーナーのボブ・グッチョーネのPenthouse Films Internationalが唯一プロデュースした映画『カリギュラ』では、実在のローマ皇帝カリギュラ(マルコム・マクダグウェル)が暴政を振るい、ローマ帝国を淫蕩へと導く姿が描かれている。それは粋な歴史映画(ゴア・ビダルが脚本を担当)とポルノ映画の”最良の部分”を融合するという挑戦でもある。だが、最終的に勝ったのは、どちらだろう? 主人公のカリギュラは、ヘレン・ミレン、サー・ジョン・ギールグッド、ピーター・オトゥールといった超一流のキャストにペントハウス・ペット(訳注:ペントハウスの表紙を飾るヌードモデル)とおしゃべりをさせたり、排泄物と精液の有意義な使い方を考えさせたりする以外は、近親相姦、レイプ、ネクロフィリア(屍姦症)を繰り返す。大失敗を回避するため、グッチョーネは6分にわたるハードなセックスシーンも加えた(ほとんどがオーラルセックスによる乱行シーン)。その結果、堕落したローマの暴君でさえ立ち止まる、あらゆる冒涜がひとつになったような作品に仕上がった。(Writer: ERIC HYNES)
9.『クルージング』(1980)Photo : Mary Evans/Ronald Grant/Everett Collection
アル・パチーノ扮する警官がSMクラブで男を引っかける連続殺人犯を追ってニューヨークのゲイ・サブカルチャーに潜入し、予想通りその世界の奥深くへと引きずりこまれる『クルージング』。伝えられるところでは、若干深入りしすぎたウィリアム・フリードキン監督にMPAA(アメリカ映画協会)はなんと映像の40分をカットさせ、当初のX指定からR指定に切り替えたそうだ。それでもフリードキン監督は、男同士のアクションシーンを模した多くのシーンをカットしようとはしなかった。ホモセクシュアリティとニューヨークのゲイ・カルチャーをめぐる不正確な描写ゆえにゲイ・コミュニティからの批判が殺到した。その結果、『クルージング』は公開と同時に大コケに終わってしまった。しかしながら、当時の悪評はある程度挽回され、いまでは1970年代末のニューヨークのダウンタウンのアンダーグラウンド・サブカルチャーを描いたタイムカプセル的な作品とみなされている。(Writer: BILGE EBIRI)
10.『ケレル』(1982)Photo : Triumph Releasing/courtesy Everett Collection
ライナー・ベルナー・ファスビンダー監督の最後の映画『ケレル』は、監督にとってもっともパーソナルであると同時に、同監督作のなかでももっとも悪評の高い作品のひとつで、そのけばけばしい不自然さとトム・オブ・フィンランド(訳注:LGBTQの権利を訴えたフィンランドの作家)にインスパイアされた舞台装置は、ファスビンダー監督の熱狂的な信奉者さえも苛立たせた(あの巨大な男性器の大道具を見てほしい!)。だが、フランスの作家ジャン・ジュネの小説『ブレストの乱暴者』を題材とした、いかにも舞台向きで様式化された同作は、極めて深奥でありながら悲しく、劇中で繰り広げられる濃密な同性同士のセックスシーンは、別世界のような雰囲気を醸し出している。ジュネの小説の映画化というよりは、原作を読み終えたファスビンダー監督の熱に浮かされた夢と夢精のような作品だ。(Writer: BILGE EBIRI)
11.『ヘンリー&ジューン 私が愛した男と女』(1990)Photo : Etienne George/RDA/Getty Images
いまとなっては内容よりも当時の公開事情のせいで有名になったフィリップ・カウフマン監督の『ヘンリー&ジューン 私が愛した男と女』。フランスの女流作家アナイス・ニンの回想録を映画化した同作は、初めてNC-17(17歳以下鑑賞禁止)に指定されたメジャー映画である。技巧的なエロティカ作品をX指定というポルノ映画の呪縛から解放するはずだったNC-17指定は、すぐに災いのもとになってしまった。というのも、多くの新聞社が比較的趣味の良い(そして大胆なまでにセクシャルな)同作の広告掲載を拒んだのだ。『ヘンリー&ジューン 私が愛した男と女』はフレッド・ウォード扮する性的好奇心に満ちた作家ヘンリー・ミラーと徐々に性の世界へと解放されていくニン(マリア・デ・メディロス)を描いた文学的なラブストーリーである。道徳の番人のような人々は、恍惚とした叫びやあえぎ声がわいせつだと非難したものの、ミラーの妻(およびニンの愛人)を丸裸で演じた若き日のユマ・サーマンがのちに正真正銘の映画スターになる妨げにはならなかった。(Writer: ERIC HYNES)
12.『クラッシュ』(1996)Photo : Fine Line/courtesy Everett Collection
デビッド・クローネンバーグ監督がイギリスの作家J・G・バラードの同名小説を映画化した『クラッシュ』を的確に表現するとしたら、卑猥以外あり得ない。自動車事故の衝撃から得る性的快感がテーマの近未来が舞台の同作は、近代性の残骸を検証し、自動車事故フェチや傷口への挿入行為といった私たちが存在することさえ知らなかったタブーを掘り起こした。ハイスピードによる絶大なインパクトの絶頂感からギプスのエロチックな可能性の探求にいたるまで、同作のセックスシーンは不快感を抱かせると同時に戸惑いを感じるほどドキドキさせられる。この上なく怪しげな主演俳優のジェームズ・スペイダーは、瀕死の事故によって性的倒錯者となったブルジョワの映画プロデューサーを演じた。その一方、俳優のイライアス・コティーズは顔に傷を負った自動車の修理工として映画史上屈指の淫乱な演技を披露した。『クラッシュ』は、その”大胆さ”が評価され、1996年の第49回カンヌ国際映画祭で審査員特別賞を受賞した。米CNNの創設者テッド・ターナーは同作を退廃的だと判断し、全力で公開を阻もうとした。(Writer: ERIC HYNES)
13.『イディオッツ』(1998)Photo : Mary Evans/Ronald Grant/Everett Collection
『アンチクライスト』(2009)と『ニンフォマニアック』を世に送り出すずっと前から、ラース・フォン・トリアー監督は社会と良識を嘲笑ってきた。フォン・トリアー監督が始めたデンマークの映画運動”ドグマ95”の唯一の作品である『イディオッツ』によって監督は初めて論争の味を占めた。同作は、知的障害者のふりをしてブルジョワ階級の自己満足から解放され、それに真っ向から立ち向かおうとする大人たちのグループを描いた希望のないブラックコメディである。挑発行為の一環として彼らはグループセックスに興じるのだが、当然ながら、その描写はフォン・トリアー監督らしい断固たるものだ(勃起した男性器のシーンもあるが、米国公開の際にデジタル処理が施された)。そのため、いくつかの国ではレイティングをめぐるトラブルに発展したが、その後のフォン・トリアー監督の作品の基準と比較すると、まるでディズニー映画のようだ。(Writer: BILGE EBIRI)

14.『アイズ ワイド シャット』(1999)Photo : Warner Bros/Courtesy Everett Collection
スタンリー・キューブリックの遺作『アイズ ワイド シャット』は、話題になったベネチアのマスクが登場する乱行シーンに加えられた監督公認のデジタル処理によってポルノ的な行為がぼかされたおかげでNC-17指定を免れた。このシーンは見事なまでにエロチックだが、同作でもっとも卑猥な場面はギリギリPG-13指定といったところだろう。豪勢なクリスマスパーティでそれぞれが別の相手とのささやかな戯れを楽しんだ後、トム・クルーズとニコール・キッドマン扮する夫婦は、ベッドルームでハイになりながら欲望について語り合う。妻が性的な誘惑に駆られるなんてあり得ないとクルーズに挑発されたキッドマンは白い下着姿になり、夏の休暇先で出会ったセクシーな海軍将校に関するモノローグを甘い声でささやきながら、夫の嫉妬心を掻き立てる。性的能力に関して言えば、その後クルーズが繰り広げる性的冒険はキッドマンと比べると色褪せて見える。(Writer: ERIC HYNES)
15.『ポーラX』(1999)Photo : Winstar Cinema/Courtesy Everett Collection
『ポーラX』は、レオス・カラックス監督による米作家ハーマン・メルヴィルの小説『ピエール』の胸が痛くなるほどパーソナルな改作である。同作は、パリのボヘミアンとして貧しいながらも小説家として生きるため、上流社会の生活から隠遁する、ふさぎこんだ青年(ジェラール・ドパルデューの息子のギヨーム・ドパルデュー)の物語だ。姉を名乗り出る漆黒の髪の美女(カテリーナ・ゴルベワ)が森から現れ、貧しい生活を送る主人公に魔法をかけたとたん、すべてがヒートアップする。カラックス監督は1980年代末に新進気鋭の若いフランス人監督として頭角を現したものの、『ポンヌフの恋人』(1991)の制作中に燃え尽きてしまった。カムバック作でもある『ポーラX』でカラックス監督は、一見優しくも貪欲な本物のセックスを俳優たちに要求した。むさ苦しい部屋の暗闇のなかで身もだえする身体は不明瞭で、芸術と残虐性との境界を曖昧にしている。野生味あふれる、どの作品よりも緊迫感に満ちたドラマを巧みに表現しているのだ。(Writer: ERIC HYNES)
16.『ベーゼ・モア』(2000)Photo : Film Fixx/Courtesy Everett Collection
「これはマスターベーション用の映画じゃない」と復讐を描いたスリラー映画『ベーゼ・モア』を手がけたふたりのフランス人監督、ヴィルジニー・デパントとコラリー・トラン・ティのいずれかが言った。「要するに、ポルノ映画ではないの」。なるほど。このように言い切ったのはコラリー・トラン・ティ監督だが、彼女をはじめ主演のカレン・ランコム(訳注:当時は「カレン・バッハ」名義で出演)とラファエラ・アンダーソンは、過去にポルノ映画に出演し、仏ポルノ映画に華を添えてきた人物だ。そんなランコムとアンダーソンが劇中であからさまなオーラルセックスや性交を行っている姿を目の当たりにすると……観客のなかには「それでもポルノじゃないの?」と混乱する人もいるだろう。古びたローファイ・スタイルで撮影され、エピタフ・レコードのバックカタログからくすねてきたようなサウンドトラックが特徴の暴力的で笑えるくらい平凡なストーリーの同作は、男のファンタジーを描いた典型的なポルノ映画というよりは、パンキッシュなB級映画に近い(本誌の映画批評家のピーター・トラヴァースは、「セックスシーンありの『テルマ&ルイーズ』だ!」と女性のエンパワーメントを描いた物語に見事になぞらえた)。だが、同作はいくつかの国ではいまだに上映禁止となっており、スクリーン上で繰り広げられるセックスシーンの膨大さをとっただけでも、同作は極めてニヒルなポルノ映画と紙一重である。(Writer:DAVID FEAR)
17.『赤い部屋の恋人』(2001)Photo : Mary Evans/ARTISAN ENTERTAINMENT/REDEEMABLE FEATURES/Ronald Grant/Everett Collection
男(ピーター・サースガード)は、ネット・トレーディングで巨万の富を得たシリコンバレーの長者で、女(モリー・パーカー)はストリッパー。男は女を金銭で雇い、ラスベガスで3日間を一緒に過ごす。女は男の前でラップダンスを披露し、男は魔法の杖のように富を振りかざす。これらすべてをウェイン・ワン監督は資本主義と肉欲をめぐる哲学論文のように取り扱っている。米HBOの西部劇テレビドラマ『デッドウッド〜銃とSEXとワイルドタウン』に出演しているパーカー本人(あるいはセックス専用のスタント)がロリポップを隠すゲームを始めるや否や、『赤い部屋の恋人』は完全に異次元のセックス・パワーゲームに突入する。(Writer: DAVID FEAR)
18. 『インティマシー/親密』(2001)Photo : Empire Pictures/Courtesy Everett Collection
イギリスの作家ハニフ・クレイシの作品を題材とし、『ラストタンゴ・イン・パリ』のテーマを再訪したパトリス・シェロー監督の2001年の映画『インティマシー/親密』。同作は、互いに素性を知らない男女が週毎に行う(非擬似)セックスに焦点を当てている。互いのことを深く知るにつれ、ふたりの人生は複雑さを増す。『ラストタンゴ・イン・パリ』同様、本物らしいセックスシーンというコンセプトとその作用について再考させられる作品だ。目の前で繰り広げられる荒々しくも濃厚なセックスシーンを見終わった後、あなたは登場人物のことをもっと深く知るようになるのだろうか? それとも、その逆だろうか? いずれにせよ、サスペンス映画『シャロウ・グレイブ』(1994)のケリー・フォックスが劇中で共演者のマイク・ライランスにフェラチオをしたことで同作は悪名を得、フォックスのキャリアは失速してしまった。それでもフォックスは、同作において史上最高の演技を披露したと主張しつづけている。(Writer:BILGE EBIRI)
19.『天国の口、終りの楽園。』(2001)Photo : IFC Films/Courtesy Everett Collection
『セロ・グラビティ』(2013)で宇宙空間を探究し、『トゥモロー・ワールド』(2006)で長回しの素晴らしさを体験する前、アルフォンソ・キュアロン監督は2001年の大ヒット映画『天国の口、終りの楽園。』でエロチックな3Pの数学的な可能性を探索した。たしかにアナ・ロペス・メルカードの豊満なバストは観客と性的に興奮したふたりの若い旅仲間にとっては魅力的なトラップだが、青年たちが相手に対して抱く欲望こそが同作のゴールである極めてエロチックでカタルシス的なグループセックスの推進力になっている。クライマックスの長い余韻のおかげで同作はMPAAのレイティングなしに公開され、忌まわしいNC-17指定を免れた。それだけでなく、主演俳優のふたりは映画スターとしての地位を確立した。(Writer:ERIC HYNES)
20.『ドリーマーズ』(2003)Photo : Fox Searchlight/courtesy Everett Collection
『ラストタンゴ・イン・パリ』で実存主義に挑んだ数年後、ベルナルド・ベルトルッチ監督はフランスのヌーヴェルヴァーグと1968年の5月革命時代を振り返り、驚くほどの寛大さとともに当時を描いた、セックス浸りの映画『ドリーマーズ』を制作した。同作では、アメリカ人留学生を演じたマイケル・ピットがエヴァ・グリーンとルイ・ギャレル扮するセクシー(そしてどことなく近親相姦的)な双子とパリのアパルトマンで同棲生活を始め、ありとあらゆる独創的なセックスにふける。ベルトルッチ監督作品にふさわしく、映画における--解放的であると同時に恐ろしくもある--セックスの可能性は無限のように見えるが、外の世界の混乱によって全員が現実に引き戻される。同作は『ラストタンゴ・イン・パリ』のような興行成績は達成できなかったものの、FOXサーチライト・ピクチャーズ(現サーチライト・ピクチャーズ)という製作・配給スタジオが財政面でのダメージを与え得るNC-17指定映画にゴーサインを出した珍しい例として注目に値する。(Writer: BILGE EBIRI)
21.『KEN PARK』(2002)Photo : Courtesy Everett Collection
ラリー・クラーク監督作のなかでももっとも物議を醸した『KEN PARK』が米国で正式に上映されなかったのは、ティーンエイジャー同士の(フェラチオを含む)非擬似セックス、3P、ボンデージ、近親相姦、さらにはショッキングな暴力を描き、あまりに挑発的だったから? それとも、単に楽曲の原盤権の権利処理の問題だろうか? 答えは永遠に闇のなかだが、ハーモニー・コリンが脚本を手がけた、中・低所得者が暮らす郊外を描いたダークな同作は、さまざまなスケーター・パンクのティーンエイジャーと、保護者たちとの複雑な(正確には「めちゃくちゃな」)人間関係を映し出している。クラーク監督とコリンの基準からしてもひねくれた作品である。ガールフレンドの母親と寝る男が同作でもっともまともなキャラクターである時点で、『KEN PARK』が普通ではないことを教えてくれる。(Writer: BILGE EBIRI)
22.『ブラウン・バニー』(2003)Photo : Mary Evans/KINETIQUE INC/VINCENT GALLO PRODUCTIONS/WILD BUNCH/Ronald Grant/Everett Collection
映画監督を志す人たちは、次のことを忘れないでほしい。映画の上映時間のほとんどを費やして主人公に事実上何もさせなくても構わないし、エンターテイメント業界の誰よりも自己陶酔的であっても結構だ--主演女優のフェラチオで映画を締めくくる限りは。これこそ、監督と脚本を手がけたヴィンセント・ギャロが自ら主演したペットプロジェクト『ブラウン・バニー』の重要点である。主人公のバイクレーサーは、じっと考え込む以外は劇中で何もしない。それでも同作が話題になるのは(ギャロと映画評論家のロジャー・イーバートとのあいだに強烈な確執が生まれたことを除き)、共演者のクロエ・セヴィニーの口のなかにギャロが”ギャラ”を突っ込んだからだ。撮影の際におそらくギャロが人工装具の男性器を使っていたからといって、このシーンを観るときの気まずさは和らがないし、このメジャー作品においてこのシーンが(何らかの)意図があることに変わりはない。観客は、世界的に有名な才能あふれる女優が自らの品位を落とす姿をワンカットで目撃する。いっそ本物のポルノ映画を観るほうが嫌な気分にならずに済む。(Writer: DAVID FEAR)
23.『ナイン・ソングス』(2004)Photo : Mary Evans/REVOLUTION FILMS/Ronald Grant/Everett Collection
『マイティ・ハート/愛と絆』(2007)のイギリスのマイケル・ウィンターボトム監督は、粗削りのロマンチックなストーリー、コンテンポラリー・インディーロック、きわどいセックス描写を通じて1970年代のアート系エロティカ作品を2000年代にふさわしいものにアップデートした。フランツ・フェルディナンド、エルボー、ザ・ダンディ・ウォーホルズ、プライマル・スクリームといったアーティストによるライブ演奏をフィーチャーした『ナイン・ソングス』は優れた作品で、時には人間関係が性的な出会いによってどのように展開するかについて新しい見方を教えてくれる。いままでの作品と異なり、『ナイン・ソングス』は女性の快楽に徹底して追求しており、その印象はセックスの最中とその後の女優マルゴ・スティリーの恍惚とした顔にもっとも長く、パワフルに刻まれている。ERIC HYNES
24.『ショートバス』(2006)Photo : Think Film/courtesy Everett Collection
セックスシーンなしにセックスに肯定的な映画を創ることはできないし、『ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ』(2001)の次にジョン・キャメロン・ミッチェル監督が手がけた『ショートバス』ほどセックスに肯定的な映画は存在しない。ニューヨークはブルックリンのサロン”ショートバス”に集う人々の恋愛生活を描いた同作では、異性同士・同性同士・カップル・3人組・本命を見つけた独身者のありとあらゆるセックスがあけすけに繰り広げられる。この手の多くの作品と異なり、ミッチェル監督のエロチックな群像コメディは、登場人物たちの悪ふざけをただのショッキングなネタとして取り扱っていない。同作では、セックスにも吸うことにも同等の価値がある。たしかに、男同士が身体中に射精したり、延々とクンニリングスが続いたりするシーンに慣れていない観客は気まずさを感じるかもしれないが、ミッチェル監督が描くグループセラピーの雰囲気は、実際に他人のセックスを見ていることを実感させてくれる。ミッチェル監督は、ほぼポルノ映画と言ってもいいような、観る人を前向きな気分にさせてくれるテンプレートを生み出した。(Writer: DAVID FEAR)
25.『ラスト、コーション』(2007)Photo : Focus Features/Courtesy Everett Collection
大日本帝国による祖国・中国の占領を阻もうと、過激派の学生グループはミスター・イー(トニー・レオン)という日本軍の傀儡政府の高官を罠にはめ、殺害するために若く美しいワン・チアチー(タン・ウェイ)をスパイとして雇う。すべては計画どおりに進むものの、イーとワンは計画を台無しにしかねないほどの情熱的な恋に落ちる。『ブロークバック・マウンテン』(2005)のアン・リー監督は、ふたりの情事の詳細を厳格なまでに描き、彼らの肉体的衝動は恐ろしさを感じさせるほどだ。こうしたシーンには珍しい長さと、頬を紅潮させた俳優たちの心地良さそうなセックスの描写により、同作はNC-17に指定された。(Writer: ERIC HYNES)
26.『エンター・ザ・ボイド』(2009)Photo : UNIMEDIA EUROPEWILD BUNCH
フランスの鬼才ギャスパー・ノエ監督のVR叙事詩『エンター・ザ・ボイド』は、幻覚状態による死後の世界の冒険を描いている。ドラッグ中毒の死んだ兄の魂は肉体を離れてネオンが輝く東京の街を浮遊するが、ずっと一緒にいるという約束を果たすため、東京でストリッパーとして裸体をさらしながら働く妹(パス・デ・ラ・ウエルタ)を見守りに現世に戻ってくる。ノエ監督作品にふさわしく、兄の魂は女性器に挿入された男性器のクローズアップと子宮頸部までの旅(女性器の内側から撮影)という形で生への復活を遂げる。(Writer: BILGE EBIRI)
27.『SHAME−シェイム−』(2011)Photo : Copyright Fox Searchlight Pictures. All rights reserved./Courtesy Everett Collection
『それでも夜は明ける』(2013)を制作する前、スティーヴ・マックィーン監督はウォール街で働くセックス依存症の男(マイケル・ファスベンダー)が主人公のダークなドラマ映画『SHAME−シェイム−』を手がけ、究極の悦楽を探し求める男の毎日を描いた。マイケル・ファスベンダーというルックスのせいで、不幸にも男は意味のないセックスを手軽に経験でき、劇中はそんなシーンであふれている。一夜限りの関係、売春宿通い、ポルノを観ながらマスターベーションにふけるランチタイムなど、この哀れな男は心の傷を癒すために誰かと絆を結ぼうとしては、失敗する。独自のスタイルを通じてマックィーン監督はこの世界の特殊さや質感から目を逸らさず、次から次へとセックスと裸体(”Fassmember”と話題になったファスベンダーの臀部も)をさらけ出す。楽しいという感情とは無縁の作品である。(Writer: BILGE EBIRI)
28.『WEEKEND ウィークエンド』(2011)Photo : Courtesy of IFC Films
アンドリュー・ヘイ監督が米HBOの人気コメディドラマ『Looking(原題)』を制作する前、ヘイ監督は長い週末に親密な関係になるふたりの男が主人公の『WEEKEND ウィークエンド』を手がけた。一夜限りの関係だと思っていたものがやがてはよりパーソナルなものへと変化するなか、ふたりは真剣な交際を望んでいないと率直に告白する一方、一連の打ち明け話を通じて疑いようのない親近感を抱く。それとともにセックスシーンはますますきわどくなり、男が身体中に射精するシーンは、観客に想像の余地を一切与えてくれない。こうしたシーンは濃密でありながらも婉曲的であり、観客はふたりの男の強くなる絆と欲望の表現を目の当たりにする。(Writer: ERIC HYNES)
29.『アデル、ブルーは熱い色』(2013)Photo : Sundance Selects/Courtesy Everett Collection
2013年に第66回カンヌ国際映画祭パルムドールに輝いた『アデル、ブルーは熱い色』は、アデルという若いフランス人女性(アデル・エグザルコプロス)が自分より経験豊富なレズビアンの女性(レア・セドゥー)との出会いを通じて成長する姿を描く。同作が果敢に挑んだ露骨なセックスシーンとレズビアンという関係に対する概して肯定的な描写は、賛否両論を引き起こした。果たして『アデル、ブルーは熱い色』は、ふたりの若い女性のあいだで育まれる愛と、やがて訪れる破局を誠実に描いた作品なのか? それとも、男性監督とふたりの異性愛者の女優が起用され、刺激的なセックスシーンが描かれている時点で妥協を強いられているのだろうか(その両方という可能性はあり得るだろうか?)? いずれにせよ、愛し合うふたりが交わす優しい眼差しは、ふたりの主演女優がさまざまな体位で延々と悦楽に興じるとくに長いシーンによって永遠に評価の対象となるだろう。(Writer: BILGE EBIRI)
30.『湖の見知らぬ男』(2013)Photo : Strand Releasing/Courtesy Everett Collection
おもに南フランスの湖畔が舞台のアラン・ギロディ監督のスローなスリラー映画『湖の見知らぬ男』では、フランクという青年(ピエール・ドゥラドンシャン)が口ひげをたくわえた魅力的な男(クリストフ・パウ)に惹かれていく様子が描かれる。フランクは、この男が殺人犯なのでは? と疑う。同作の過激でありながらも爽快な点は、男のヌードと男同士のセックスをいかに普通なもの、ましてやありきたりなものとして描いていることだ。だからといって、茂みのなかの隠れたセックスがスリリングじゃないとか、同作が人気のいない場所でのセックスシーンを出し惜しみしているとかではない。エキゾチックな未開の自然というよりは、その場の風景の一部としてこうしたシーンを見せつけられるほうが、なぜかずっとドキドキするのだ。(Writer: ERIC HYNES)